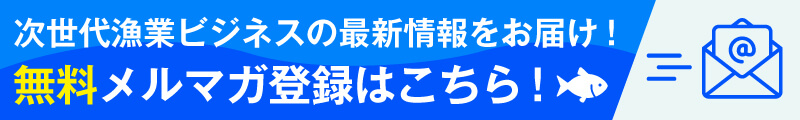【ツアーレポート】海洋ごみの現状や循環型社会を学ぶ、大人の修学旅行in長崎対馬
2025/10/01

美しい海岸線に広がるのは、海洋ごみや、磯焼けといった深刻な環境課題。日本一海洋ゴミが漂着する島・対馬を舞台に、漁業や資源再生の現場を訪ね、循環型社会の必要性を肌で感じるツアーが開催された。環境問題を「自分ごと」として考え、学ぶ3日間の記録。
1.自然豊かな離島の今を知る 3日間の「大人の修学旅行」
2.対馬の漁業と海洋漂着ゴミの現実
3.日本で最も多く海洋ゴミが漂着する島から「ごみゼロアイランド」へ
4.海の未来を形づくると信じて、今できることを
自然豊かな離島の今を知る
3日間の「大人の修学旅行」
長崎県対馬市。九州と韓国の間に浮かぶ「国境の島」は南北に長く、周囲の海には好漁場が形成され、複雑に入り組んだリアス海岸が絶景を描く。島の約9割が森林で希少な照葉樹原始林があり、ツシマヤマネコなど固有の生き物が生息する。豊かな自然、歴史や文化、食など、さまざまな魅力が詰まった島だ。
2025年7月中旬、「海の今を見にいこう 大人の修学旅行in対馬」が催行された。主催は、ヤシノミ洗剤など環境に配慮した製品で知られるサラヤ株式会社。森や川、その先の海の環境保全への取り組みにも力を入れていることでも知られる同社が、その輪を消費者にも広げようと初めて企画。旅には社員やキャンペーンの当選者ら15人が参加した。
ツアーの目的は、雄大な自然や海産物に恵まれた対馬の魅力を体感しつつ、この島が直面する環境の変化を肌で感じること。2泊3日に多彩なテーマが詰め込まれている中でも、核心は、浜辺に打ち寄せられる海洋漂着ゴミの現場を自分の目で見ることにある。私たちを取り巻く海について理解を深める旅が始まった。
 対馬の入り組んだ美しい海岸線と澄んだ海
対馬の入り組んだ美しい海岸線と澄んだ海
対馬の漁業と
海洋漂着ゴミの現実
イカやアナゴ、アジ、サバ、タイ、クエ、タチウオなど多種多様な魚介類が水揚げされる対馬では、漁業は主要産業の一つだ。漁船に乗り、漁業の現場へ。有限会社丸徳水産が手がけるサバ養殖は、定置網にかかった小さくて市場に出せない魚を漁業者から買い取って蓄養し、エサも対馬の海で獲れたものを用いて実施している。天然ものだけでは難しい安定供給につながり、脂がのってサイズも大きくなり、価値が向上。漁業者の収入が増えることにもつながり、対馬の漁業存続を考える上でも大きい。
 丸徳水産の生け簀で泳ぐサバ。海にも漁業関係者にも優しい循環型漁業を掲げる
丸徳水産の生け簀で泳ぐサバ。海にも漁業関係者にも優しい循環型漁業を掲げる
箱メガネで海中を覗くと、磯焼けが進んで海藻がなくなり、岩がむき出しとなった海底が広がっていた。海藻が密集する藻場がなくなると、これまでいた海の生き物が棲むことが難しくなり、魚が減る要因になる。磯焼けの原因の一つとされるのが、温暖化。暖海性のイスズミやアイゴが海藻を食べてしまうことも影響している。
丸徳水産では、独特の臭みがあって食用には適さないとされる魚「イスズミ(愛称:そう介)」の利活用にも取り組む。「そう介プロジェクト」と名付け、食材にすべく試行錯誤を重ね、素早くさばけるよう包丁のしなり具合も自分たちで調整。その身をメンチカツに加工した「そう介のメンチカツ」は、2019年に「Fish-1グランプリ」で国産魚ファストフィッシュ部門グランプリに輝いた。
初日の夕飯は、丸徳水産が経営する「肴や えん」でいただく。イスズミのメンチカツとアイゴのフライは、臭みを感じることなく、白身魚の料理として味わった。

改良した包丁でイスズミを素早く処理

イスズミのメンチカツとアイゴのフライ
夕食前には、丸徳水産の隣に工場直売所を構える一般社団法人daidaiに立ち寄った。「獣害から獣財へ」をテーマに野生鳥獣被害対策に取り組み、シカやイノシシを肉や革などの資源にする活動などを行っている。対馬では、シカやイノシシによる農林業被害が深刻化し、有害鳥獣として駆除している。山の下草が食い尽くされて土の中の栄養が減り、むき出しの山肌は雨で土砂が一気に流れて海を茶色く変色させてしまう。
丸徳水産は漁師が案内する養殖や磯焼け現場の見学、生け簀での餌やりなどの体験ツアー「海遊記」を、daidaiはハンターによる山の捕獲現場や解体・加工の作業などを見学するツアー「Meet meat」を提供している。両者は「海と山がやせていくのを食い止めたい」という想いで連携し、「持続可能な海と山を繋ぐ伝承ツアー」も始まった。海と山のバーベキューを味わうこともできる。

山の中に仕掛けられた箱罠
日本一海洋ゴミが漂着する島から
「ごみゼロアイランド」へ
2日目はまず、島の東側の赤島海岸へ。美しいはずの海岸線には、色とりどりのプラスチック片やペットボトル、発泡スチロール、漁具など、無数のゴミが打ち上げられている。

劣化したゴミが海岸を覆いつくす赤島海岸
今回の旅のガイド、一般社団法人対馬里山繋営塾(けいえいじゅく)代表理事の川口幹子さんに促され、ゴミを踏みしめてみる。ふかふかと沈み込むような感触を記憶し、西側のクジカ浜へ向かった。軍手をはめて清掃の準備をし、海岸へ降りると、ここにも大量のゴミが流れ着いた光景が広がっていた。一般社団法人対馬CAPPAの方々から話を伺いながら、ペットボトルを集める。拾ってもゴミが減ったと実感できない徒労感。ラベルを見ると、韓国や中国、東南アジアからもたどり着いたことが分かる。CAPPAのメンバーが「外国のゴミが多いと感じるかもしれませんが、日本のゴミが太平洋に流れ出ているということもあります」と解説する。他人ごとではなく、自分ごと。作業しながら、できることは何かと自問自答する。
川口さんが「東と西のゴミの違い、分かりますか?」と問いかけた。西側のゴミは比較的新しく、東側は劣化していたり粉々になったりしている。
海流に乗って西海岸に漂着し、あふれたゴミが東海岸へ。ここでも上陸しなかったゴミはさらに海を漂い続けるのだという。漂流中にプラスチックはマイクロプラスチックとなり、生態系や人体にも影響を及ぼし、深刻な社会問題となっている。海岸は清掃してもまたすぐ、ゴミがやってくる。終わりの見えない現実が目の前にある。

クジカ浜。袋いっぱいに集めてもゴミが減ったと感じられない
拾い集めたゴミが届けられる再処理施設も訪ねた。海を漂ったゴミは汚れや塩分が付着、紫外線で劣化し、簡単にリサイクルできない状態。分類し、人の手で異物を取り除き、膨大な時間と労力をかけて資源化できる状態にしていく。それでもなお、海洋漂着ゴミの再形成物は品質もよくなく、処理する機械が止まることも多いという。高額な処理費用は、9割を国が補助するものの、残りを人口約2万5000人の町で負担するのはあまりに重い。資源化と言えば聞こえはいいが、簡単にはいかない、きれいごとでは済まない現状が、ここにもある。

海を漂った発泡スチロール(奥)と家庭ゴミでは色も耐久性も異なる
サラヤは2024年1月、グローバル規模での海洋問題解決を掲げる子会社、株式会社ブルーオーシャン対馬を設立した。漂着ゴミの資源化、漁網や漁具のリサイクル方法の確立などに取り組み、循環経済(アイランドモデル)の実践と普及を目指している。代表には今回のガイドを務める、川口幹子さんが就任した。ツアーの参加者が真剣なまなざしで「そもそもゴミを出さないことを目指さなければいけないですね」と語ると、川口さんが大きくうなずいた。
海の未来を形づくると信じて、
今できることを
ツアーでは民泊でお世話になり、対馬の人たちの朗らかな人柄に触れた。海の幸や畑の野菜は、素材とおもてなしの心が融合した料理となって振る舞われ、胃袋も心も満たされた。海中鳥居が有名で龍宮伝説が残る和多都美神社を参拝。ツシマヤマネコのいる施設を見学し、シーカヤックも満喫した。

シーカヤックを体験。海のレジャーも対馬の魅力
自然が織り成す美しい光景と、環境問題。その両方が同じ場所に存在していることが強く印象に残る。対馬の今は、日本の、世界の、目を背けてはいけない問題を凝縮して映し出しているように感じる。
生活と海はつながっている。3日間の濃密な「大人の修学旅行」で学んだことを、日常の中で生かしていかなければと決意した。その輪を広げていくことも重要だろう。一人では微力でも、日々の選択や行動が、海の未来を形づくると信じて。
PROFILE
ライター
金山成美

立命館大学卒。元神戸新聞社記者、デスク。新聞社では長くスポーツを担当、2013年から4年間の明石市担当時に水産の取材に力を入れる。書籍「あかし本~時のまちを創る 海のまちに生きる~」「明石の誇り 海の恵み」など執筆。海の当事者に共感し、漁業や海に関する発信や企画などを手掛ける、一般社団法人neo-waveの代表理事も務める。
取材・文/ 金山 成美